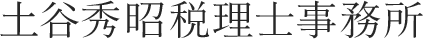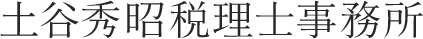相続税の節税対策方法とその効果について②
2025/04/24
ご覧いただきありがとうございます。
それでは、これから数回に分けて「相続税の節税対策方法とその効果について」説明させて頂きます。
Ⅰ 知っておきたい8つの相続対策
1 暦年贈与による節税対策の方法
相続税の対策を行う上で最もメジャーな対策は生前贈与です。
その中に年間110万円の財産がゼロ円で、子や孫に移せる方法(暦年贈与)があります。
暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を納める通常の贈与のことを暦年贈与といいます。
これは、「A財産を減らす方法」です。
|
対策方法 |
年間110万円の範囲内で贈与する(契約書作成) |
|
効 果 |
年間110万円まで非課税 |
⑴ 暦年贈与の効果
贈与税は、年間110万円の基礎控除があり、その範囲で贈与する分には税金がかかりません。(※年間110万円を超えたら税金がかかります。)
贈与税の非課税枠となる制度を利用すると財産をゼロで移すことができます。
手続きが簡単なのは、現金や預貯金などの金融資産を贈与することですが、贈与できる財産に制限はありません。
例えば、子2人、孫8人の合計10人にそれぞれ1年間で100万円ずつ贈与すると、贈与税の基礎控除額の110万円以下のため贈与税はかからず、1年間で1,000万円税金を納めることなく贈与することができます。
また、これを10年間続けていれば、10年で1億円、20年間続けていれば20年で2億円の財産を税金ゼロで移すことができる計算となります。
⑵ 暦年贈与を行うときの注意点
毎年、同じ相手に同じ金額を贈与していると連年贈与(贈与を毎年繰り返し行うこと)とみなされて税率が一気に上がり、高額の税金がかかってくる場合があるので注意が必要です。
連年贈与とみなされないために注意する点は4つです。
① 毎年同じ日に振り込むのではなく、時期をずらす。
② 金額を少しずつ変える。
③ 年によっては、110万円を少し超える贈与を行って、贈与税を納めておく。
④ 子どもの進学や入学にあわせて贈与する。
など工夫をして連年贈与に当たらないことを示す必要があります。
上記の4つのポイントを踏まえた上で、暦年贈与を効率的に行えば相続税の節税を行うことが出来ます。
また、贈与を行う際は、「本人が自らの意思であること」や「いつ、誰から誰に、いくら贈与を行ったのか」を客観的に証明するために「贈与契約書」を作成しましょう。
相続開始前(死亡前)3年以内(令和6年1月1日以後の贈与は、7年(緩和措置があります))に行われた贈与については相続財産に加えて計算しなければならない点も注意が必要です。これは基礎控除の年間110万円以下の贈与であっても適用されるので注意してください。
そうならないためにも生前贈与は元気なうちに早めから開始し、長い時間をかけて財産を分けましょう。
なお、法定相続人でも、相続又は遺贈により財産を取得しない場合は、相続財産に加える必要はありません。
なお、令和5年度税制改正で「Ⅱ章の1 相続時精算課税制度の適用による節税対策の方法」(後日、説明させていただきます。)の方がメリットが大きい場合がありますので専門家に相談してください。
----------------------------------------------------------------------
土谷秀昭税理士事務所
住所 : 福岡県福岡市南区大橋1-21-12
SWEET ALYSSUM OHASHI 4-D号室
電話番号 : 092-555-4638
FAX番号 : 092-555-4641
福岡市で計画的な相続対策
----------------------------------------------------------------------